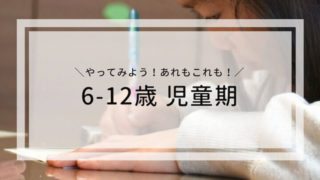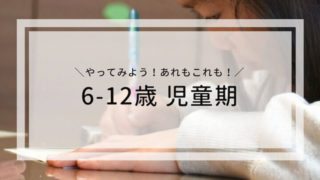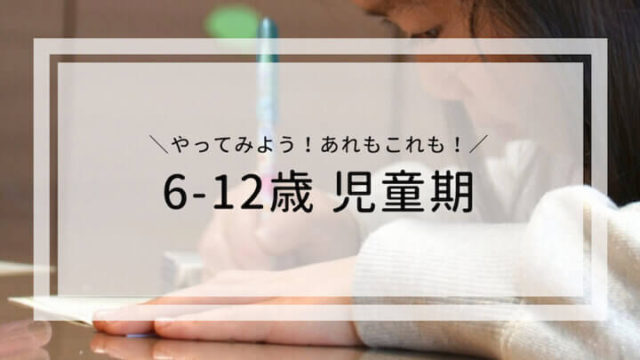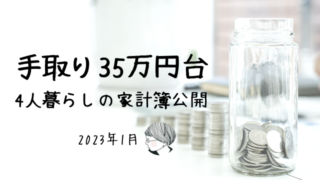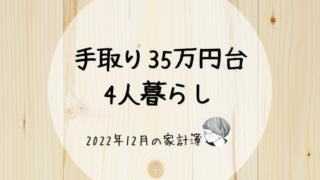突然ですが、小学生の不登校の人数はご存知ですか?
小学生の不登校は208人に1人。
学年が上がるたびに増えて、中学生になると33人に1人が不登校になる
というデータが出ています。
無責任に「学校なんか行かなくていいよ」という話ではありませんよ。
僕も親の立場なので「自分の子が不登校になったら…」と考えます。
父親の視点で掘り下げていきますね。
小学生の不登校は何人に1人?


文部科学省の発表(2016年度)によると、不登校の小学生は全国で31,151人。
小学生は全国で6,491,834人だそうなので、208人に1人が不登校。
小学校低学年から高学年へ。
小学校から中学校へ。
年齢が上がるほど不登校も増えます。
ちなみに、中学生は33人に1人。
2006年度は小学生「302人に1人」に対し、
2016年度は「208人に1人」。
そう考えておくのは、無駄なことではありません。
小学生の不登校の何が問題なのか。
「我が子が不登校になったら?」考えておきましょう、とは言いましたが、
小学生の不登校を問題視しなくていい理由
不登校を問題視しなくていい理由を、発達心理学の立場から説明すると
「小学生時代=社会の中に居場所を見つけていく時期だから必ずしも学校に行かなくていい」です。
そうなんです。
社会に役立つ技術を身につけられるよう援助するのが学校。
不登校を心配し過ぎる必要はない、というのはそういうことです。
大切なのは、誰かのためになる力をつけること。
それによって、自分の居場所を作っていくこと。
それって学校でしかできないことですか?
そんなことありませんよね。
バイオリン職人を目指してたよね。彼は中学生だけど。
小2作の手作り帽子が、神がかってる!
確かに勉強は大切ですが、一方でこんな話もあるんです。
》不登校になった小学生の女の子 自宅で趣味の才能を磨く姿に称賛の声(別サイト)
不登校になった小学2年生の女の子が、大好きな裁縫の腕を磨き自信を深めていくエピソード。
僕はこのストーリーに強い希望を感じました。

これを追求していけば、社会の中に自分の居場所を作っていけるでしょう。
小学生の時期の人間として、もっとも理想的な発達です。
本気でうらやましいくらい。
発達心理学的には、こういうのを幸福と呼びます。
もちろん大人のサポートが欠かせませんし、学校ほどノウハウが確立していないので
簡単ではないですけどね。
この女の子の場合も、ご家庭ではとんでもない努力や苦労があったと思います。
小学生の不登校の原因
どれも今ココにいられない状態ですよね。
いろいろな要素が絡んでいますが、
結局は「居場所がない」と感じることで不登校になるんです。
なお、不登校の原因を学年ごとに分けて考えることがありますが、
たぶん無意味です。
「今すでに楽しくない」
「将来マシになる見込みがない」
それでは学校に行きたくなるわけがありませんよね。
小学生の不登校への対応、どうすればいい?
小学生の不登校への対応の話を書きます。
一応、学校は大切なところ!
基本的には、学校には通った方がいいです。
勉強以外の経験もたくさん積めるからです。
娘(小2)を見ていても思います。
というわけで、無理やり通わせる必要はないけれども
不登校にならないに越したことはないんです。
楽しく小学校に通えるように!
では、どうすれば楽しく通えるようになるのか?
幼稚園・保育園時代からできることは何か?
お子さんが6、7歳であっても、3、4歳であっても同じ。
子供の気持ちに「いいね(イエス)」で応えること。
充実した気持ちを、さらに高めること。
幼児は特に、意欲的によく遊ぶことですね。
小学生も同じ。
遊んでばかりはいられないでしょうが、
そうすれば、前向きな気持ちが強くなります。
居場所を作る努力も、楽しくできるでしょう。
小学生の不登校 まとめ
学校には、基本的には通うべき。
そう書きましたが…、
小学生の時期、それが心の発達の最優先課題。
学校は、単なる手段。
他の手段を選んだっていいのです。
上で紹介した小2女子の話は、すごくわかりやすいですよね。
子供「学校に行きたくないっ!」
親 「這ってまで行くよーなとトコじゃないよ。休め休め」
子供「裁縫のお店を開きたい!」
親 「お店で困らないように算数の勉強をしよう!」
と、意欲的な生活を送っているわけです。
親のサポートあってこそだと思います。
苦労の多い道ですが、子供の充実した人生を考えるとやってみる価値は大きいですよ。
小学生の不登校についての記事はこれでおわりです。
他にも記事を書いていますので、読んで頂けると嬉しい。