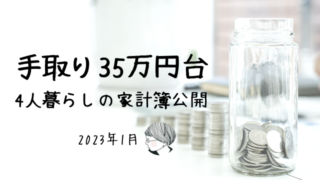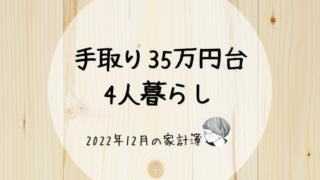「自分の子育て、これでいいの?」
さまようあなたの道しるべ、あります。
こんな疑問を抱えている方におすすめです。
- 赤ちゃんって、ずっと抱っこしてなきゃいけないの?
- 1歳になり、何でも「ジブンで!」やらせるべき?
- 幼稚園はお勉強系?遊び系?
- 小学生になり、不登校に…。どう接するべき?
発達心理学者エリクソンのライフサイクル・モデルをヒントに、疑問を解決していきましょう。
長年受け継がれ、研究が重ねられた「心の取扱説明書」ですから、きっと役に立ちますよ!
エリクソンの「ライフサイクル・モデル」とは
こんなふうに、大人の方が自分の人生を見つめるのにも役立つライフサイクル・モデルですが、今回は…
まずはこの図をどうぞ
「ライクサイクル・モデル」を図解


母親も仕事してて愛情が不足気味だったのもあって、2~3番目くらいの「積木」がうまく積まれなかった感じ
ということで、ブロックごとに見ていこう
ライフサイクル・モデル(1)|赤ちゃん期


⇒0歳から1歳くらいに強くしたいブロック。
親しい大人との信頼関係の中で生活することで、人生のあらゆる場面で希望を持てるようになります。
0歳児は、「人間関係に対して希望を持つ」こと自体を練習しています。
だから、赤ちゃんが「希望を持てる」関わり方が最高。
おまけとして、重要な事実を。
ライフサイクル・モデルを通してエリクソンが伝えたかったこと、それは、
その時期にはその時期の「能力」を磨こう、ということ
そうしておくと、その後の人生で、まったく異なる場面でも、その「能力」を使えるようになるんですよ。
赤ちゃんを例に見てみます。
→学校の友人、会社の同僚、誰とでも信頼関係を築ける
赤ちゃんは毎日練習してるんですね。「希望を持つ」練習を。
→赤ちゃん期の悩みまとめ記事(作成中)
ライフサイクル・モデル(2)|よちよち期


2番目のブロックは、よちよち期
⇒1歳から3歳くらいに強くしたいブロック。自分の意欲が尊重される生活の中で、何事にも意欲的になれるマインドが手に入ります。
「いろいろなことに対して意欲を発揮できる」という、これまた超スゴイ能力が育まれます。
整体に詳しい人は「独立期」なんて呼ぶんだとか。
このくらいの歳の人間は要するに、「自分でどんどん決めて、実際やる」ことで、そういう力をつけたがってるんでしょう。まさに「独立」。
※2018年中ごろには「ブラブラ期」という名称もバズりました。
「独立」のエネルギー源は「意欲」ですよね。
「意欲」の練習を繰り返すことで、自由に「意欲」を使えるようになっていく、というわけ。
この「能力」も、将来とても役立ちます。「何かが楽しくて仕方ない」人間になるわけですからね。
ある実業家の方は、「僕は意欲的な人間しか採用しません。意欲だけは大人になってから鍛えようがないから」とまで言ってました。
ライフサイクル・モデル(3)|幼児期


3番目のブロックは、幼児期
⇒3歳から6歳くらいに強くしたいブロック。
前の段階で手に入れた意欲をとことん深めるイメージ。自分の気持ちを遠い目標に向け、諦めずにそれを達成していく気持ちが育ちます。
「必要と感じたことを諦めずに達成する能力」の大きさが、この時期にかなり決まるとされています。
この年齢の子供は、とにかく遊び込まなければなりません。そして、遠くに設定した遊びのゴールをひたすら目指します。
遊びの目標を達成するためには、諦めないこと。諦めず遊び込む経験が積み重なると「諦めない」人間になるんです。「諦めない練習」です。
「諦めない」ことの中には、こんなことも含まれます。
- 他人と協力する
- ケンカを乗り越える
- 感情をコントロールする
「遠くの目標」に向かって一歩ずつ進みたいのですから、ムカついたりケンカしたりしてる暇はないんですよね。
OECD(※)もこの「能力」を非常に重視していて、「保育園・幼稚園がんばれ!
世界の未来はこの時期にかかってるぞ!」と言っています。
このような力は「社会情動的スキル」と呼ばれ、各国でデータを集めているところです。
※経済協力開発機構Organization for Economic Cooperation and Developmentのこと。アホっぽい説明だが、世界中で役立つ研究を積み重ねている組織。
ライフサイクル・モデル(4)|児童期


4番目のブロックは、児童期(小学校の時期)
⇒6歳から12歳くらいに強くしたいブロック。目標を達成しようと思う気持ちを元に、与えられた課題を自分の目標として捉え直してクリアしていく段階。
「世の中で間違いなく生きていける」という自信を持てるかがカギです。
自分が生きる世界で、誰かの役に立つ「能力」を身につけたいのが、この「児童期」。
※別名「学童期」
小学生が学ぶのは、誰かの力になれる技術でなければなりません。
「受験のための知識」を好きになれる人には幸せでしょう。それはそれで「誰かを助けられる力」になりますしね。
でも、受験勉強が苦手・好きではない人にとっては?小学生が不登校になるとしたら、そんな理由がありそうですよね。
家庭科や音楽が、上手でなくても好きになれる環境が、発達心理学的には望ましいです。
学校関係なしに、例えばスケボーを究める(きわめる)んだっていいんですよ。将来スケボーの演技で勇気を与えられる人になるかもしれませんし。
親がそれをわかっているだけで子供は救われるでしょう。「楽しんで、本気で追求できるなら、それは勉強じゃなくてもいいんだよ」って。
ライフサイクル・モデル(5)|自分探し期


⇒中学生以降に強くしていくブロック。
誰かに強制されることなく、自分の気持ちに素直に向き合った上で、「あ、自分ってこういう人間なんだな」と腑に落ちるのがこの段階。
自分探しは、まったくの0(ゼロ)から始まるわけではありません。エリクソンは「仲間集団」の影響が強いと言います。
クラスの友人、趣味の仲間、同じ思想のグループ、どれもが「仲間集団」です。
自分が属する「仲間集団」は複数あっても問題ありません。いくつかの「仲間集団」を試すのが普通です。
※「中2病」は、今までの自分とは違う「仲間集団」を試している状態。
そのようにして、「自分はこういうオリジナルだ」と自覚を深めていきます。
自覚が深まりきると「自分探し」終了です。早い人で20歳くらいでしょうか?
この段階からは特に、個人による年齢の幅が広がります。
体の発達を見るとわかりやすいですよね。男性で言えば、声変わり。声変わりの時期って、早い人は11歳より前で、遅いと14歳を過ぎてからなんです。
心の発達も、大きな変化が始まるのが早い人・遅い人がいます。見守る大人は焦らずに待ってあげるといいでしょう。
「いい子」でいることを強要されてたり、逆に早く大人にさせられたりすると、「偽りの自己」になりやすいみたい
青年が、無意識においても邪魔されず「自分」を作り上げた時、本当の意味で子育ては終わり。
育てられていた人は、次は子育てする人になっていきます。
ライフサイクル・モデル(6)|結婚生活期


⇒結婚生活の期間に強くなるブロック。
いったん完成した自分と、もう一人の完成した「誰か」が混ぜ合わさって、一つの共同体ができる。 つまり結婚生活。
「子育てじゃなく、夫婦生活の話?なぜ?」
そう思うかもしれません。しかし夫婦関係は子育てに直結しています。
パートナーとして共に育つ、ということは子育てという戦場を共に生き抜く戦友になるということ。
夫婦どちらかが死んだら子どもも危険。それが子育てですから、夫婦お互いがしっかり生き残れるようになっていなければいけません。
もちろん、お互いの心が、です。
結婚生活期に「成功」があるとしたら、そういうことでしょうね。
例えばどんなことが大変だった?
毎日気持ちを伝え合って初めて「戦友」になれると思うけど、伝えるべき意見が特になかったって感じ。
30歳くらいで準備が整って、「いいと思う・良くないと思う」って伝えられるようになった
ちなみに、それぞれの段階で得られる「能力」に、エリクソンは名前をつけています。
赤ちゃん期なら「希望(hope)」
よちよち期なら「意志(will)」
結婚生活期に身につく能力の名前は
ウソみたいですが、ちゃんと発達心理学の教科書に載ってる単語。
赤ちゃんは「希望を感じる練習」をして「希望を感じる力」を身につけます。
1歳児は「意志を使う練習」を重ねて「意志を使う力」を身につけますね。
夫婦はお互いに「愛す練習」を繰り返すことで「愛す力」を身につけるんですよ。
すると、何がおこるか?
パートナー以外も「愛する」ことができるようになるんです。
もちろん、自分の子供もね。
ライフサイクル・モデル(7)|子育て期


⇒子育ての期間に強くなるブロック。
夫婦生活期に得た「愛」をもとに子供を育てることで、未来に残るものを育てる力が身につく。男性にも欠かせない発達段階。
結論から言えば、命がけで子供を育てることで、「育てる力」が身につく時期。
「育てる力」が自分のものになると、どうなるでしょう?
人間の子供を育てるのが上手になる、というだけじゃないですよ。
「今後残っていくもの」を育てる力がつくのです。
例えば、誰かの発言・行動・アイデアを受け入れ、もっとよくするために自分にできることを考えられます。「育てよう」という気持ちが普通になる。
☑親として
☑上司として
☑友人として
何も育てられない人になります。
何にも責任を負いたくない状態。
このような特徴をエリクソンは「拒否性」と名付けました。
これは「すべてを拒否する力」ですから、
・誰かの発言
・誰かのアイデア
・誰かの行動
すべてを拒否し続ける人になっていきます。
「育てる力」はcare(ケア)。
7番目の「積木」である子育て期を命がけで乗り切った人は、世の中のいろんなことをケアできる人になれるんですね。
ライフサイクル・モデル(8)|円熟期


最後、8番目のブロックは、円熟期
⇒老年期に強くなるブロック。子育てを終える、仕事を終えるなどして、人生を振り返りながら最後を迎える時期。
矛盾だらけの自分と社会の歴史すべてを認められるようになる。
いやね、想像はできるんだよ。でもまだ経験してないから、読んでくださってる方に「こうですよ!」って伝えられない
誰か知らない人とも、自分の子と接するイメージで関われるようになるのかな?とか
世界を・誰かを呪いながら死んでいくの?と思ったらゾッとする…
まとめ(一覧表あり)
というわけで、「子育てに生かすためのライフサイクル・モデル」の解説でした。
最後まで読んでくださったあなたが、少しでも楽しく子育てできることを願っています。
また、
そう悩むあなたが、1つでもヒントを見つけられたなら嬉しく思います。
| 【大体の年齢(名称)】 | 【求めていること】 | |
|---|---|---|
| 1 | 0~1歳 (赤ちゃん期) |
「希望」を持てるように関わってほしい |
| 2 | 1~3歳 よちよち期) |
「意志」を大きく、適切に使いたい |
| 3 | 3~6歳 (幼児期) |
「目的」に向かって遊び込みたい |
| 4 | 6~12歳 (児童期) |
好きなことを通じて「居場所」を作りたい |
| 5 | 12歳~ (自分探し期) |
仲間との交流を繰り返して「自分」になりたい |
| 6 | 22~30歳? (結婚生活期) |
夫婦で「戦友」になりたい |
| 7 | 30~45歳? (子育て期) |
未来に残るものを育てたい |
| 8 | ~死 (円熟期) |
人生の総まとめをしたい |
主に1〜4(赤ちゃん~小学生)のこと。
「子育て」という時、子供の年齢は何歳までなのか?
エリクソンによれば、「少なくとも6歳までをしっかり育てることが、
親の発達(7番目のブロック)のためには欠かせない」とのこと。
子供自身が
「希望」
「意欲」
「目的」
を大きく伸ばせるよう援助し、
その力をもとに、小学生期には「居場所」を見つけられるよう支える。
そんな視点で、今後も発信していきますね。
ぜひご期待ください!